人間の集団行動と社会のダイナミクスを数理モデルで解き明かす
2024.08.29
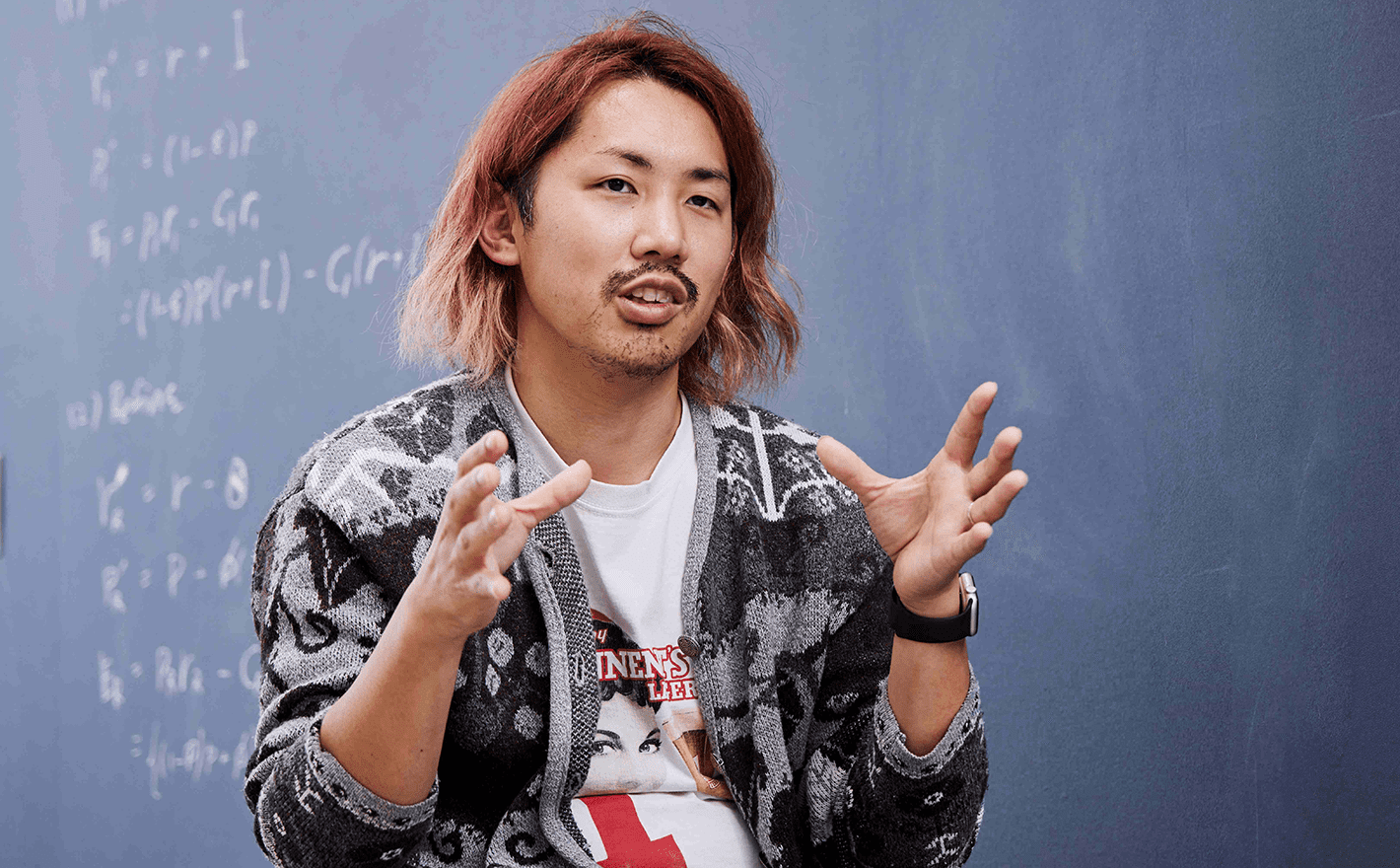
人間の行動は、集団の意思決定や情報、流行などに大きく影響される。それは必ずしも人間社会に特有な現象というわけではない。動物行動学、進化生態学などの多くの研究者が記述し、解析してきたように、ミツバチが多数の個体で女王蜂を中心とするクラスターを形づくる様子や、チンパンジーが多数派に同調して行動したり、優位の個体のマネをするなど、ほかの動物でも知られている。それらの知識をベースに、BTCC 計算論的集団力学連携ユニットの豊川航ユニットリーダー(以下、UL)は、人間を対象に社会的学習や集団意思決定について数理モデルで解析を行ってきた。
2023年春、コンスタンツ大学(ドイツ)から理研CBS-トヨタ連携センター(BTCC)に着任した豊川ULが、「あまり理研らしくないテーマだが」と語る研究の対象は人間の集団だ。その集合知や集団意思決定のメカニズムとそこから生まれる文化進化を解読している。
行動生態学や群集生態学などマクロな生物学のおもしろさに開眼したのは北海道大学水産学部の学生時代だった。進化生態学や数理生態学にも初めて触れ、「嫌いじゃなかった数学の力を借りて生物のシステムを理解できるようになることに衝撃を受けた」という。やがて興味は魚類や昆虫の集団生物学に。さらに「人間社会も、動物を対象にした数理生態学と同様の発想で分析できるのではないか。人間の社会活動や文化現象のはやりすたりの時間的な変動も微分方程式で捉えられそうだ」と考えたのが、今に至る研究者としての歩みの発端だった。以来、「火星人だって社会関係における意思決定のロジックは成り立つはず」と、人間行動と社会のシステムを数理生物学的アプローチで解き明かす研究を意欲的に続けてきた。
人間の行動研究を目標に、大学院では社会心理学を専攻する。所属した研究室は文系ながら、集団意思決定の理解に計算論モデルを導入するなど、サイエンスの方法にこだわるユニークなところだった。文・理の境界を超えた学際的な環境でまとめた博士論文は、「ヒトはミツバチにおける集団採餌のような集合知を発揮できるのか」がテーマだ。ヒトの社会をマクロな生物学の対象とする数理的な研究は、当時はまだ少数派だった。
博士号取得後、セント・アンドリュース大学(スコットランド)社会学習・認知進化研究センターでケビン・ララ(当時:レイランド)研究室に加わる。ララは、動物行動研究の豊富な経験から、魚類や鳥類に見られる文化の伝達と言えそうな数々の現象に注目し、模倣行動などの社会的学習が認知機能の進化につながったとする文化と遺伝子の共進化を唱えていた。ニッチ構築理論の提唱者の一人としても広く知られている。
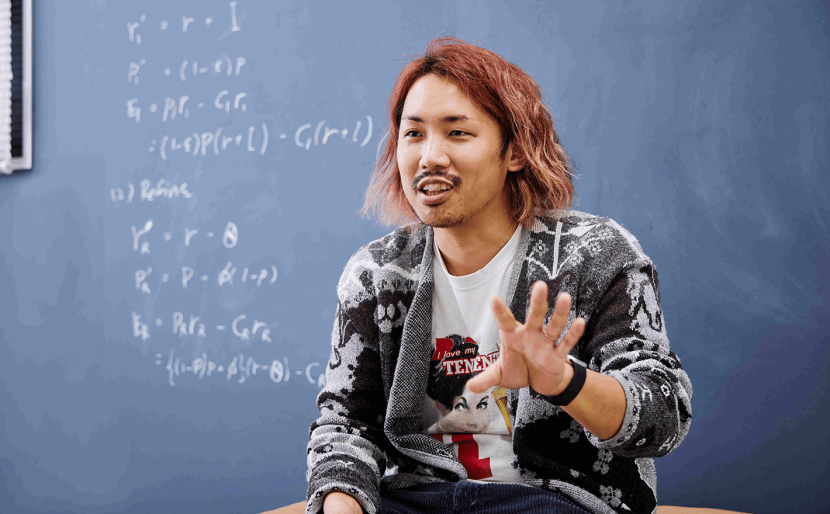
新しい理論的な主張を立ち上げて広める際には、進化生物学者や科学哲学者を交えて議論し、戦略的にアピールする様子も垣間見る機会があった。サイエンスはインクルーシブに進めるべきだとの主張をもって活動するララからは、研究社会を歩むうえで多くのヒントをもらったという。ララの一般向け著書『人間性の進化的起源―なぜヒトだけが複雑な文化を創造できたのか』が豊川ULの手で翻訳され、多くの読者を得ている(2023年勁草書房刊)。
次に身を置いたコンスタンツ大学心理学部は、動物の集団行動学、人間の意思決定科学、コンピュータ科学などの研究者が多数在籍する魅力的な環境だった。近隣にはマックス・プランク動物行動研究所もあった。コロナ感染の拡大で、意思決定研究はコンピュータゲーム実験が中心だったが、集団規模と集合知の関係について、アリの集団行動の数理モデルから人間の社会学習行動のモデルをつくった。
BTCCのポストに応募したのは、BTCCのビジョンが社会の基礎的な問題のパターンを認識してその理解を深めることと知って、社会ダイナミクスへの自らの関心と共通すると感じたことが動機だ。着任してみれば、「研究室を置く脳神経科学研究センターには数理モデルを使って生物の問題を解こうとしている研究者が何人かいて、ヒトを対象にしている私とは分野が違っても共通の方法を使っているから、話が通じる」。手がけたい複数のテーマについて想を練りながら、新しい研究室での活動に力を注ぐ日々だ。
「文系的な学問は本質的に難しい課題を扱うので、いったいサイエンスで立ち向かえるのだろうかと思うかもしれない。でも、諦めずにやってみると、面白いテーマがたくさんある。進化生物学や集団行動学は社会科学と案外深く繋がっているんです」。若い人たちにはそう伝えたい。

(取材・執筆 古郡悦子 / 撮影 古末拓也 / 制作 サイテック・コミュニケーションズ)
