人間の集団行動と社会のダイナミクスを数理モデルで解き明かす
人間の行動は、集団の意思決定や情報、流行などに大きく影響される。それは必ずしも人間社会に特有な現象というわけではない。動物行動学、進化生態学などの多くの研究者が記述し、解析してきたように、ミツバチが多数の個体で女王蜂を中心とするクラスターを形づくる様子や、チンパンジーが多数派に同調して行動したり、優位の個体のマネをするなど、ほかの動物でも知られている。それらの知識をベースに、BTCC 計算論的集団力学連携ユニットの豊川航ユニットリーダー(以下、UL)は、人間を対象に社会的学習や集団意思決定について数理モデルで解析を行ってきた。
2023年春、コンスタンツ大学(ドイツ)から理研CBS-トヨタ連携センター(BTCC)に着任した豊川ULが、「あまり理研らしくないテーマだが」と語る研究の対象は人間の集団だ。その集合知や集団意思決定のメカニズムとそこから生まれる文化進化を解読している。
行動生態学や群集生態学などマクロな生物学のおもしろさに開眼したのは北海道大学水産学部の学生時代だった。進化生態学や数理生態学にも初めて触れ、「嫌いじゃなかった数学の力を借りて生物のシステムを理解できるようになることに衝撃を受けた」という。やがて興味は魚類や昆虫の集団生物学に。さらに「人間社会も、動物を対象にした数理生態学と同様の発想で分析できるのではないか。人間の社会活動や文化現象のはやりすたりの時間的な変動も微分方程式で捉えられそうだ」と考えたのが、今に至る研究者としての歩みの発端だった。以来、「火星人だって社会関係における意思決定のロジックは成り立つはず」と、人間行動と社会のシステムを数理生物学的アプローチで解き明かす研究を意欲的に続けてきた。
人間の行動研究を目標に、大学院では社会心理学を専攻する。所属した研究室は文系ながら、集団意思決定の理解に計算論モデルを導入するなど、サイエンスの方法にこだわるユニークなところだった。文・理の境界を超えた学際的な環境でまとめた博士論文は、「ヒトはミツバチにおける集団採餌のような集合知を発揮できるのか」がテーマだ。ヒトの社会をマクロな生物学の対象とする数理的な研究は、当時はまだ少数派だった。
博士号取得後、セント・アンドリュース大学(スコットランド)社会学習・認知進化研究センターでケビン・ララ(当時:レイランド)研究室に加わる。ララは、動物行動研究の豊富な経験から、魚類や鳥類に見られる文化の伝達と言えそうな数々の現象に注目し、模倣行動などの社会的学習が認知機能の進化につながったとする文化と遺伝子の共進化を唱えていた。ニッチ構築理論の提唱者の一人としても広く知られている。
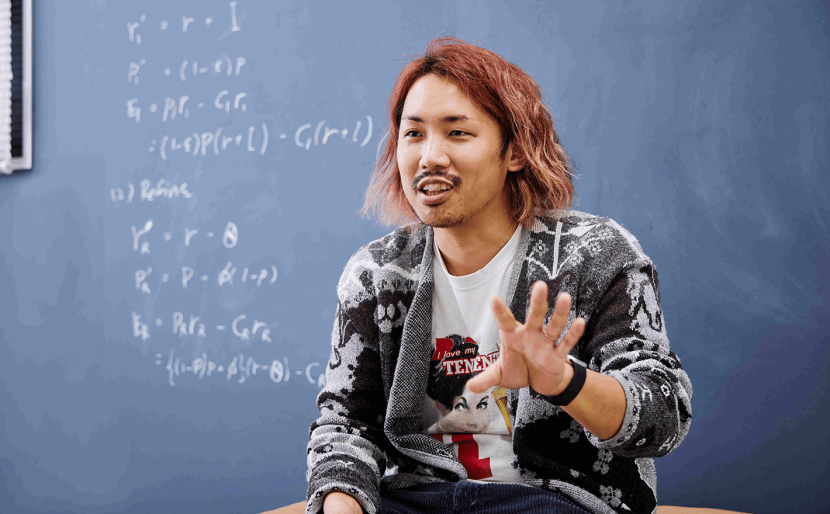
新しい理論的な主張を立ち上げて広める際には、進化生物学者や科学哲学者を交えて議論し、戦略的にアピールする様子も垣間見る機会があった。サイエンスはインクルーシブに進めるべきだとの主張をもって活動するララからは、研究社会を歩むうえで多くのヒントをもらったという。ララの一般向け著書『人間性の進化的起源―なぜヒトだけが複雑な文化を創造できたのか』が豊川ULの手で翻訳され、多くの読者を得ている(2023年勁草書房刊)。
次に身を置いたコンスタンツ大学心理学部は、動物の集団行動学、人間の意思決定科学、コンピュータ科学などの研究者が多数在籍する魅力的な環境だった。近隣にはマックス・プランク動物行動研究所もあった。コロナ感染の拡大で、意思決定研究はコンピュータゲーム実験が中心だったが、集団規模と集合知の関係について、アリの集団行動の数理モデルから人間の社会学習行動のモデルをつくった。
BTCCのポストに応募したのは、BTCCのビジョンが社会の基礎的な問題のパターンを認識してその理解を深めることと知って、社会ダイナミクスへの自らの関心と共通すると感じたことが動機だ。着任してみれば、「研究室を置く脳神経科学研究センターには数理モデルを使って生物の問題を解こうとしている研究者が何人かいて、ヒトを対象にしている私とは分野が違っても共通の方法を使っているから、話が通じる」。手がけたい複数のテーマについて想を練りながら、新しい研究室での活動に力を注ぐ日々だ。
「文系的な学問は本質的に難しい課題を扱うので、いったいサイエンスで立ち向かえるのだろうかと思うかもしれない。でも、諦めずにやってみると、面白いテーマがたくさんある。進化生物学や集団行動学は社会科学と案外深く繋がっているんです」。若い人たちにはそう伝えたい。

(取材・執筆 古郡悦子 / 撮影 古末拓也 / 制作 サイテック・コミュニケーションズ)
コミュニケーションする2人の脳活動をハイパースキャニングで計測 「Well-beingダイナミクスの解明を目指して」
社会課題としての「well-being」が、政策、経営、教育、医療など各方面で注目されている。WHO(世界保健機構)によれば、well-beingとは「個人と集団が経験するポジティブな状態」。これまで豊かさの指標とされてきたGDP(国内総生産)にかえて、人々が幸せに暮らせる社会の指標として盛んに取り上げられるようになった。それに伴い、well-being研究も活発だ。新たなモビリティーの可能性に取り組むトヨタは、人間をより深く知ることで快適な製品を生み出すヒントを得たいと、理研との連携に期待する。一方、Well-beingダイナミクスを脳神経科学で培った知見と技術によって明らかにすることを目指すBTCC個体間脳ダイナミクス連携ユニットの小池耕彦ユニットリーダー(以下、UL)は、人と人のコミュニケーションから生まれる共感を2人同時のfMRIイメージングによって観察し、コミュニケーションにおける神経基盤の理解を深めようとしている。コミュニケーションはwell-beingの重要なテーマの一つだ。
小池ULは、「well-beingとは、“いい感じ”と言い表すのが一番ピッタリです。何かしていて楽しい。持続的に起こるポジティブな状態」と話す。ほかの人と感情や感動を共有することは、心が弾む楽しい経験だ。仕事や暮らしをスムーズに進める鍵でもある。そんな状態を科学的に解析することができるのだろうか。それにはどんな方法があるのだろうか。小池ULは、人と人との関わり合いが生む共感をハイパースキャニング(複数同時脳活動記録)で調べる研究を進め、2人の脳活動を同時に計測できる装置を活用して、コミュニケーション研究を展開してきた。
コミュニケーションをしている2人の脳の活動状態をfMRI(機能的磁気共鳴画像)で同時にスキャンし、相関を調べる。fMRIは血液中のヘモグロビンが酸素と結合すると磁性が変化することを利用して、脳活動によって血流の変化が生じている部位を高い空間解像度で画像化する装置だ。2人の脳活動の相関を知るには、別々の部屋に1台ずつ設置された装置に実験参加者が入り、2人にオンラインでコミュニケーションをしてもらう。そしてそれぞれの脳活動を同時に計測する。
「人と人のコミュニケーションは協力関係です。一方的な伝達ではなく、互いの理解や同意、問いの予測や答えの期待などを含む相互作用です」。得られたそれぞれのfMRI画像を解析すると、2人が相手に注意を払いながら対話しているときには、脳活動のパターンが類似する共鳴現象が起きていることが読み取れる。さらに、「同じ画像を見て感想を話し合ったときに、感情が相手の反応によって増幅するかどうか。それもハイパースキャニングで見られるとよいと思っています」と、視覚と言語コミュニケーションを組み合わせた状態の解析にも取り組みたいと考えている。いま、人と人のコミュニケーションは対面で語り合うばかりではなく、オンラインやSNSよって、離れたところでのやり取りも盛んに行われる。対面とバーチャルなつながりで、共鳴の様子はどう違うのだろうか。
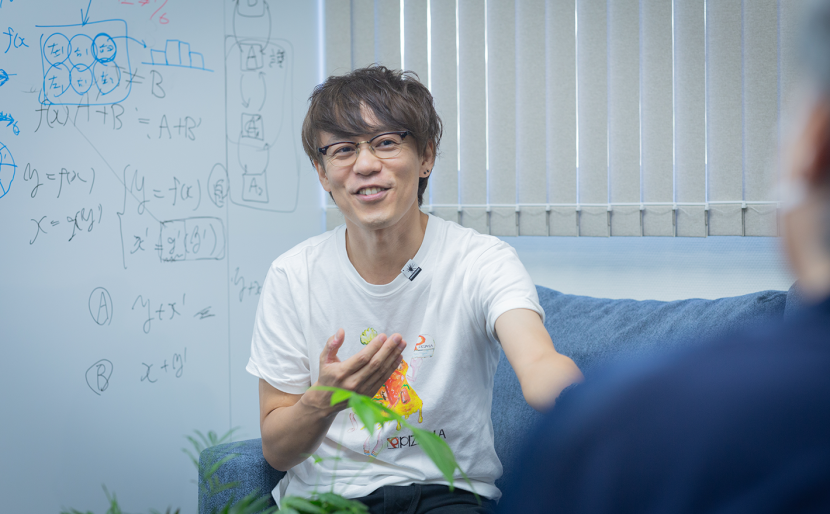
課題はまだある。ハイパースキャニングで観察される共鳴現象は果たしてコミュニケーションの結果なのか、それとも良いコミュニケーションの原因なのか。また、コミュニケーションが行われたときに脳内では実際に何が起こっているのだろうか。研究の次の目標はどうして共鳴現象が生じるかを解明することだ。 「どんなメカニズムが働いているかについて、数理モデルを作って説明したいと考えています。脳の形が類似しているほど共鳴しやすく、また脳の興奮性細胞と抑制性細胞のバランスが良いとコミュニケーションがうまくいくことは知られていますが、人と人の間で情報がどう伝わるかはまだほとんど分かっていません。仲立ちになる脳の神経細胞がどう繋がっているのか、モデルを作って説明したい」。また、「研究者が、こうするとwell-beingが向上すると示し、それを企業や社会が社会設計や制度設計に活かしてくれると良いと思う」と、研究成果の社会への還元に期待を寄せる。
小池ULは、社会の人々とのコミュニケーションから得るところが多いと言う。「研究目的に集中している私たちと違って、研究者でない人たちが何を考えているかを知ることは、研究の大きな刺激になる」と、理研公開日には見学者との会話を楽しむ。BTCCが拠点とする理研脳神経科学研究センターに所属する研究者の研究分野は、医学、神経生理学、心理学、認知科学、人工知能、画像解析など極めて多彩だ。その中で、小池ULは「ひとところに様々な背景を持つ研究者がいる環境はたいへん刺激的」と、研究生活の充実を実感している。
(取材・構成 古郡悦子 / 制作 サイテック・コミュニケーションズ)
クルマ、脳、ヒトの本質 - ユニークな連携で“Well-beingな社会”の進展を
自動運転車やスマートホ-ム技術、環境に優しい建物などが集結し、実際に人々が生活するテストベッド(技術検証コミュニティ)であるコネクティッドシティ。自動車メーカーのトヨタがこの都市プロトタイプを発表した時、注目のほとんどはそのデザインやモビリティ―・ソリューションに集まっていた。しかし、2021年に着工されるこのコネクティッドシティやほかの同じような実験コミュニティが成功するかどうかは、テクノロジーではなくバイオロジーに大きく依存するのかも知れない。あちこちに設置されているセンサーや新しいマシンを住民はどのように利用し受け入れるのか、そしてこのような環境が対人関係や生活の質にどのように影響するのか。これらはこれから答が出されていくであろう課題だ。
進化するコミュニティや未来社会の心理的な観点を研究するため、トヨタは自然科学の総合研究所である理化学研究所(理研)の脳神経科学研究センター(CBS)と連携している。2007年に設立された理研CBS-トヨタ連携センター(BTCC)は、心、身体、個人そして集団がどのようにWell-beingを達成し向上しうるか、という問いにその研究の焦点を移しつつある。
脳研究と自動車会社は自然なパートナーには見えないかもしれない。だが、BTCCセンター長の國吉康夫氏は、理研とトヨタは長期的な目標を共有していると言う。「ヒトの性質の深い理解に基づいた“より良い未来の社会”を、我々は創りたいのです。すべてのモノと人が繋がるよう設計された都市で、人々の良い生活や生きるモチベーションを担保できるのか?新しいサービスやモビリティ様式はどのように社会やコミュニティの形成に影響するのか?そして、何が都市を楽しく活き活きとさせるのか?BTCCはこれらのメカニズムを明らかにしたいのです」國吉氏は語る。日本語的にゆるく翻訳するならば、その指針は「脳科学が先導する活気のある社会の実現」である。
これらの抽象的で学際的な問いに挑むにあたり、BTCCは過去のドライビングの研究、脳卒中後のリハビリや脳と身体のつながりの研究などにおける過去の実績を足場にしている。BTCCで既に確立している北城圭一氏と下田真吾氏それぞれが率いる研究ユニットは、脳卒中後の運動や認知機能の回復を評価し、改善する新たな方法を発見したり、脳機能のうち熟練した運転に貢献する因子を研究したりしてきた。
赤石れい氏が率いる新規BTCCユニットは、意思決定の科学を基盤としながら、人が不慣れな状況において、どのように信頼を確立し、良好な関係やコミュニティをデザインできるのかを研究していく。このユニットは、どのように人間と機械や人工知能を調和させることができるのかも同時に研究していく。
今後、3つのユニットはそれぞれの研究の結果や手法を応用し、Well-beingの要素を探求し特定するという、この連携の目標に向かっていく。例えば、筋肉の凝りから集団や社会ネットワークにおける意思決定行動まで、身体および精神の個人差データを集積することで、ヒトのより高次なレベルの感情状態を研究者が予測するのに役立てる。そして、この高次レベルの感情状態の予測によって、今度はコネクティッドシティのようなWell-beingを推進させる良好な環境をどのようにデザインできるのか、についての情報を得ることができる。
「Well-beingには身体の健康からメンタル面、ソーシャル面の健康など、様々な観点がある」と國吉氏は語る。「BTCCが擁する3つの研究ユニットは、これらの観点に個別に焦点をあてて研究し、さらにそれらを統合していきます。Well ‐beingの具体的な測定方法や、基礎研究をより大きなスケールでの成果へとつなぐ具体的な方法を見出だしたい、と我々は考えています」
我々人類がポスト産業社会へと移行していく中で、10年以上にわたり脳科学と工学の融合分野で積み重ねてきた研究実績を武器に、BTCCはヒトの性質を方程式に組み込むという課題に挑むのにうってつけの位置にいるといってよいだろう。
インタビュー&英語原文:Amanda Alvarez
